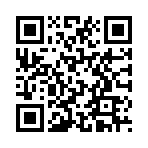2012年12月23日
<ゆく河のながれは絶えずして、
しかも、もとの水にあらず>
・・・
「方丈記」(鴨長明)の古典の校訂と現代語訳を手がけた浅見和彦さんは話す。
約8600字、原稿用紙22枚ほどの随想を貫くのは、確かに無常観だろう。
一切は消滅を繰り返し、変わらずに在ることはない。その確信が冒頭の一説に集約する。<ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず>
長明が生きた時代は災厄と戦乱が続いた。
・・・死臭漂う無秩序な街で、それでも人々は富と出世に執着し、人をうらやみ、さげすむ。
「そこへ自身の人間関係のもつれや職業上の挫折も重なり、彼は出家を選んだ。ただそれは決して後ろ向きではなく、むしろ無常にこそ希望を見ようとする所に作品の魅力がある」(浅見さん)
遁世といいながら、晩年の長明はとにかく、よく歩いた。
近隣はもちろん、57歳にして鎌倉へも出向いている。
<つねに歩き、つねにはたらくは、養生なるべし>
日野に結んだ庵も、実は組み立てと分解が簡単にできる移動式だったという。
絶えず清浄の新天地を求める心意気がそこにある。
♪しあわせは歩いてこない/だから歩いてゆくんだねーー長明が追い求めた無情の世の生きざまとは、そういうことなのだろ。
12/23 読売日曜版より 文:宇佐美仲
すごく、共感するので掲載する。
・・・
「方丈記」(鴨長明)の古典の校訂と現代語訳を手がけた浅見和彦さんは話す。
約8600字、原稿用紙22枚ほどの随想を貫くのは、確かに無常観だろう。
一切は消滅を繰り返し、変わらずに在ることはない。その確信が冒頭の一説に集約する。<ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず>
長明が生きた時代は災厄と戦乱が続いた。
・・・死臭漂う無秩序な街で、それでも人々は富と出世に執着し、人をうらやみ、さげすむ。
「そこへ自身の人間関係のもつれや職業上の挫折も重なり、彼は出家を選んだ。ただそれは決して後ろ向きではなく、むしろ無常にこそ希望を見ようとする所に作品の魅力がある」(浅見さん)
遁世といいながら、晩年の長明はとにかく、よく歩いた。
近隣はもちろん、57歳にして鎌倉へも出向いている。
<つねに歩き、つねにはたらくは、養生なるべし>
日野に結んだ庵も、実は組み立てと分解が簡単にできる移動式だったという。
絶えず清浄の新天地を求める心意気がそこにある。
♪しあわせは歩いてこない/だから歩いてゆくんだねーー長明が追い求めた無情の世の生きざまとは、そういうことなのだろ。
12/23 読売日曜版より 文:宇佐美仲
すごく、共感するので掲載する。
2012年10月30日
月刊誌「育てる」10月号掲載
エッセイ7 駄菓子屋カフェ
池田 庭子
子どもと一緒にいると新鮮な驚きに多く出会う。
以前、限界集落といわれる静岡市街地から車で1時間ほどのところに、築100年前の空家を借りて、『たぬきむら』を創り、お泊り体験を毎週引き受けていたころの話である。
壊されていたかまどを再現して薪でご飯を炊き、閉じられていた囲炉裏を掘り起こし、自在鍵をつけて鍋をつるして味噌汁をつくり、囲炉裏の炭の火に金網を乗せて街から持ってきた秋刀魚を焼く。
炭が高いから村の人にいただいた薪を燃やして炭を作るが、家の中は煙でモウモウ。何回もお泊りに来る子どもはこの煙にも慣れて、むせたり咳き込んだりしなくなる。
味噌汁の具は、山ん中のお豆腐屋さんの豆腐と油揚げで決まり。水がいいのか素朴で本当においしい。
出しは煮干と昆布と椎茸を浸す。
味噌は学生たちと一緒に味噌作りしたもので、薪で大豆を炊き、石臼でつぶしたものを山の酵母菌と家の酵母菌が住んでいるところに1年寝かすとそれはそれは「村の娘」にあったような味である。
こどもたちと一緒に夕食をつくって、味噌汁をどんぶりに盛り、囲炉裏の回りに囲んで食べる。
子どもたちがどんぶりの味噌汁を3回もおかわりする姿をお母さんは知らないだろうなあと当時思った。
秋刀魚の骨もしゃぶって皿もなめるようにして食べる。昼間、蜂の巣を見つけ退治した蜂の子をフライパンで囲炉裏で炒って、人差し指でつまんでためし食いなどして遊ぶ。
夕食の片付けの後も囲炉裏に座って、火箸をもって、囲炉裏の火をいじり、灰をきれいになでつけている。
「火って、いいもんだなあー」
「えっ」
4年生の留生くんが、背を丸めてつぶやいたのが聞こえた。おじいさんみたいことをいうと思わず顔を見る。ゆったりと時間をすごしている姿がほほえましい。
「明日も泊まっていい?」と、金曜日になると電話が留生くんから入る。一緒にバスに乗って1時間バスに揺られて『たぬきむら』に通った。土曜日は柔道のお稽古の日だが『たぬきむら』に行くならお稽古は休んでもいいと、ご両親からも絶大な信頼であった。
この留生くんは小学1年からお泊り体験をして、私が『たぬきむら』の理事長を退任するまでの間、6年生まで続いていた。今はもう高校3年生になり、駄菓子屋カフェに顔見せてくれた。
今日の駄菓子屋カフェでは、4時から「はなうたカフェ」を開いていた。「はなうたカフェ」とは気楽に鼻歌ぐらいで楽しむ時間よ。そこに、4年生の男の子、大村くんと杉山くんが入ってきた
「『瀬戸の花嫁』」知っているよ。
「(時代が違う!)えっ、どうして?」(時代が違(う!)
この二人は静岡鉄道少年団に入っていて、「鉄ファン」というだって。鉄ファンの二人は、パソコンを使い「駅メロ」(電車の発車音楽)を出す。
「岡山駅の5~8番乗り場は『瀬戸の花嫁』だよ。
『いい日旅たち』は高松駅・岡山駅で使われるけど、使われないときも。『桃太郎』は・・・」と続く。
「すごいなあ」
「4年生だよ。このぐらい知らなきゃ。ねー。」
だって! 言うじゃん!
「瀬戸内海は海がきれいだよ。島がきれいだよ。海の上を散歩したい」
「海の上を散歩したい」とすらりと言ってのける子どもに感銘しているところに、高齢の方が見えた。
「瀬戸内海・八重島・石垣島・利尻島・に行ったよ」
「じゃあ、尖閣諸島にいったことある?」
ぎゃっ、尖閣諸島に結びつく子どもに脱帽じゃ!
楽しいな・ぬっくいな・きらきらと・むちゅうになって・ららららら…の願いをこめて、子どもたちの遊び場を創ってきた。このことは八坂村が原点であった。
青木先生に1年間のエッセイをといわれたときは、「冗談」でしょとお断りしたが、ここまで書けたのは皆様の暖かい励ましをいただいたからこそで、心より感謝する。また、八坂10期の國分さん、岡村さん、編集の三井さんとも新たに出会えたこともうれしい。
2012年09月29日
月刊誌「育てる」9月号掲載
エッセイ 駄菓子屋カフェ
池田 庭子
駄菓子屋カフェ連載4で「コロンビア白熱教室」の〈選択〉についてふれた。それをお読みくださった岡田 寛(山村留学修園生保護者)さんが、 NHKテレビで放映されたコロンビア大学ビジネススクールのシーナ・アイエンガー教授の「コロンビア白熱教室」シリーズ5回分のCDを送ってくださったのである。私はシリーズで欲しかっただけに貴重な資料に感動した。
早速、CDを差し込んで観る。
第1回の「あなたの人生を決めるのは偶然?選択?」というなかで、「あなたのなかで運命を変えた選択と思われる事柄を述べてください」と質問がでた。
聞きながら自分はと振り返ってみた。
私は人生の中で大きく運命を変えた選択が2つ思い浮かんだ。
そのひとつは、私が40歳代のときであった。
生涯の仕事と思っていた会社が倒産。残務整理して山梨県大月市初狩町にある「瑞岳院」で座禅三昧の日を1週間ほどして、山を下った。
友人のご夫妻から電話をいただいた。
「ニューヨークに遊びに行こう」
お金が何もないのに、お誘いである。
「お金がない」
即答で断る。
「金貸してあげるから一緒に行こう」
三度目のお誘いに乗ることに。
でも借りるのはいやだから電話の権利を売ってピアノを売ってなどとお金を工面する。
メトロポリタン美術館を観て、ニューヨークでビジネス鞄が気に入って買うことにした。
「その鞄、使う道あるの? 大丈夫?」
友人は心配した。
「うん」と私は小さく頷く。
この鞄を持って仕事をしている姿を想像した。
それからすぐである。
社員教育の仕事に入っていった。
いきなり社員教育の仕事? とこれを読んだ人は思うでしょうが、ここで述べると長くなるので又の機会にしますが、ニューヨークで買った鞄が私にとって人生の選択となったといって過言ではない。
もうひとつは、バブルがはじけて社員教育の仕事がなくなったときである。
当時、早稲田大学大学院教授深沢道子氏の講座を申し込んであった。カウンセリングの講座で、本も出版されているその題は「心配性をなくす」であった。
「池田さんは?」
教授から昼休みに声がかかった。
「打ちひしがれています」
「あら、よかったわね」
「えっ」
「時間ができたじゃない」
「そうっか、時間が出来たのか」
家に帰ると、新聞の社会人学生募集が目に入った。
そして、私は52歳で大学生になった。
そして、大学生になったのがきっかけで、大学内の売店のオーナーになった。
私にとって挑戦であったが、運命を変えた選択であった。
子どものケイタイ電話が鳴った。
子どもはケイタイを耳に強く押し当て頭を垂れて、「ごめんなさい。ごめんなさい」と繰り返している。
夕刻5時の門限に、時計は5時半になっていたのだ。
小学5年のこの子は親から罰として、「1ヶ月間駄菓子屋に行ってはいけない」と言い渡されたと後で聞く。
「でもね、お母さんは約束の時間に帰ってきたことないんだよ」とも言っていた。
「そうかあ」と聞きながら、親のしつけと矛盾の中で、子どもの責任と選択が訓練されているのかわかりかねるが、アイエンガー教授は「選択こそ力なり」。「選択する能力」。「今日の自分を明日なりたい自分へと変える唯一の手段、それこそ選択の力なのである」と第1回目で説いていた。
ともあれ、私にとって八坂での出会いは人生の原点であり、人生を豊かにしてくれる。
2012年01月05日
「育てる」寄稿つづき
ぜんかいのつづき
平成十年、まだ生涯学習とはなんぞやの時代で、社会人学生が珍しい時代であった。
娘が三月に卒業したその翌月の四月に私は学生となった。
ガイダンスは仕事の都合上欠席となるところを娘が身代わりになって出席してくれた。学士資金も娘が保証人となって育英資金を借りることができた。余談であるが返済が滞ると今は東京にいる娘のところに督促状が行き「おい、おい」と、電話があったことがあった。娘が身代わりとなって大学生活のスタートを切ることができ、娘が保証人になってくれたおかげで親が大学に行けるとは親のエゴなのかとおもいながらも、こんな孝行娘はいないなあと親ばかになる。しかし娘が素直に親を支援してくれる考えをもったのも八坂が原点にあると思う。
大学生活は金銭的にも体力的にも四年間続くとはおもっていなかったが、前期・後期と半年半年とつないでいるうちになんとか卒業が出来た。これもひとえに応援してくれた教授たちや娘たちの支援の賜物とおもっている。感謝感謝である。
生涯学習学科で学んだことは、理論から実践へ、実践から理論で理解を深める鍛錬をしないと人間は成長しないということ。そして私の生涯のテーマとなったのは子どもの成長にとってもっとも大切なことは、自然の中での遊びやありふれた日常生活であり、これらを通じて心豊かな感性や思いやりの心をはぐくみ生きていく力となる『未来を担う青少年が心豊かに育つ場を提供する』となった。
この考えの原点はやはり八坂にある。八坂で自然と人がふれあいのなかで生きている子どもの姿を見たわたしはその後の私自身の人生観となった。
お世話になった農家は裏の仁科さんちと長女は曽山の諏訪さんちであった。「婿が居なかったら八坂から婿を送るからなあ」と長女に声をかけ、母親一人で娘二人を育てている私には「池田さん離婚しちゃあだめだ」と酒の話かは忘れたが異端なき声で心底身内のようにして言ってくれた農家のかたがたのあったかさは未だに忘れえぬ宝である。
平成十年、まだ生涯学習とはなんぞやの時代で、社会人学生が珍しい時代であった。
娘が三月に卒業したその翌月の四月に私は学生となった。
ガイダンスは仕事の都合上欠席となるところを娘が身代わりになって出席してくれた。学士資金も娘が保証人となって育英資金を借りることができた。余談であるが返済が滞ると今は東京にいる娘のところに督促状が行き「おい、おい」と、電話があったことがあった。娘が身代わりとなって大学生活のスタートを切ることができ、娘が保証人になってくれたおかげで親が大学に行けるとは親のエゴなのかとおもいながらも、こんな孝行娘はいないなあと親ばかになる。しかし娘が素直に親を支援してくれる考えをもったのも八坂が原点にあると思う。
大学生活は金銭的にも体力的にも四年間続くとはおもっていなかったが、前期・後期と半年半年とつないでいるうちになんとか卒業が出来た。これもひとえに応援してくれた教授たちや娘たちの支援の賜物とおもっている。感謝感謝である。
生涯学習学科で学んだことは、理論から実践へ、実践から理論で理解を深める鍛錬をしないと人間は成長しないということ。そして私の生涯のテーマとなったのは子どもの成長にとってもっとも大切なことは、自然の中での遊びやありふれた日常生活であり、これらを通じて心豊かな感性や思いやりの心をはぐくみ生きていく力となる『未来を担う青少年が心豊かに育つ場を提供する』となった。
この考えの原点はやはり八坂にある。八坂で自然と人がふれあいのなかで生きている子どもの姿を見たわたしはその後の私自身の人生観となった。
お世話になった農家は裏の仁科さんちと長女は曽山の諏訪さんちであった。「婿が居なかったら八坂から婿を送るからなあ」と長女に声をかけ、母親一人で娘二人を育てている私には「池田さん離婚しちゃあだめだ」と酒の話かは忘れたが異端なき声で心底身内のようにして言ってくれた農家のかたがたのあったかさは未だに忘れえぬ宝である。
2012年01月03日
育てる会寄稿1
下記は社団法人育てる会 機関紙「育てる」の寄稿文である。
昨年の十二月でした。
家に帰ると留守電がピカピカ点滅していた。
メッセージを聞くと「育てる会の青木です。また明日電話します」
懐かしい。何年振りでしょう。長女と次女は十期生でお世話になった。
八坂の風や山々や八坂の人々と子どもたちの声が走馬灯のようにつながる。
懐かしさで早速連絡を取ると寄稿の依頼であった。しかも1年間である。大役である。
笑い飛ばしたが、結果受けることに。
「出来るか出来ないかやってみなければわからない」未熟者の私は、怖いなあとおもいながら前に進むことにした。
今回はプレスタートとして自己紹介兼ねてお話させていただく。
「やってみなければわからない」
「やっていくうちにおのずとこたえがでてくる」と、まだ見ぬ世界に冒険するといえばかっこいいが私の乱暴な生き方は、五二歳で大学生になり、一八歳の現役の学生らと一緒に進級し彼らと一緒にNPO法人を立ち上げ子どもの遊び場、たのしいな・ぬっくいな・きらきらと・むちゅうになって・らららららと願い「たぬきむら」を創って活動。
学生たちと活動しているうちに大学から声がかかり大学内売店新設の「Yショップ」を経営することに。そして二〇一一年三月、街の中に定住型「居場所」としての役割と静岡の駄菓子屋文化の継承も視野に入れて「駄菓子屋カフェ」を開店する。
「ナゼその歳で大学生になったのですか」とよく訊ねられる。
あれは、早稲田大学院の文学部教授のセミナーを受けていたときで平成十年のときであった。
「池田さん、どうですか」
「はあ、リストラの雨に打たれて、打ち拉がれています」
「あら、よかったわね」
「えっ・・・」
「時間が出来たじゃない」
「・・・」
「そうか、時間が出来たんだ」
よかったわねと言われたときには、教授はお金の苦労がわからないんだわと声にこそ出さなかったが腹の中でおもった。 そして次の言葉の「時間が出来たじゃない」という言葉が胸に沁みこんだ。
そうだ、時間が取れたんだ。今まで忙しい忙しいで子どもたちともふれあうゆとりがなかったが時間が取れたんだと気持ちが切りかわり、帰路に着く。
長女は大阪の大学を卒業し静岡の家に戻ってきていた。
久方ぶりで家族らしい夕食に団欒の雰囲気を味わっていた。
娘は台所で夕食後の食器を洗ってくれていた。
わたしは静岡新聞を広げた。のんびりとページをめくると、
「常葉学園大学教育学部生涯学習学科新設、第1期生募集・社会人学生募集」の活字が目に飛び込んできた。
台所に居る娘に何気なしにいった。
「受けてみようかな」
「受けたら」
(一瞥されると思ったが、そうかそうきたか)
「そうね、受かるかわからないうちから悩んでもねえ」
「お金のことも頭脳のことも体力のことも受かったときに考えても遅くないよね」
つづく
昨年の十二月でした。
家に帰ると留守電がピカピカ点滅していた。
メッセージを聞くと「育てる会の青木です。また明日電話します」
懐かしい。何年振りでしょう。長女と次女は十期生でお世話になった。
八坂の風や山々や八坂の人々と子どもたちの声が走馬灯のようにつながる。
懐かしさで早速連絡を取ると寄稿の依頼であった。しかも1年間である。大役である。
笑い飛ばしたが、結果受けることに。
「出来るか出来ないかやってみなければわからない」未熟者の私は、怖いなあとおもいながら前に進むことにした。
今回はプレスタートとして自己紹介兼ねてお話させていただく。
「やってみなければわからない」
「やっていくうちにおのずとこたえがでてくる」と、まだ見ぬ世界に冒険するといえばかっこいいが私の乱暴な生き方は、五二歳で大学生になり、一八歳の現役の学生らと一緒に進級し彼らと一緒にNPO法人を立ち上げ子どもの遊び場、たのしいな・ぬっくいな・きらきらと・むちゅうになって・らららららと願い「たぬきむら」を創って活動。
学生たちと活動しているうちに大学から声がかかり大学内売店新設の「Yショップ」を経営することに。そして二〇一一年三月、街の中に定住型「居場所」としての役割と静岡の駄菓子屋文化の継承も視野に入れて「駄菓子屋カフェ」を開店する。
「ナゼその歳で大学生になったのですか」とよく訊ねられる。
あれは、早稲田大学院の文学部教授のセミナーを受けていたときで平成十年のときであった。
「池田さん、どうですか」
「はあ、リストラの雨に打たれて、打ち拉がれています」
「あら、よかったわね」
「えっ・・・」
「時間が出来たじゃない」
「・・・」
「そうか、時間が出来たんだ」
よかったわねと言われたときには、教授はお金の苦労がわからないんだわと声にこそ出さなかったが腹の中でおもった。 そして次の言葉の「時間が出来たじゃない」という言葉が胸に沁みこんだ。
そうだ、時間が取れたんだ。今まで忙しい忙しいで子どもたちともふれあうゆとりがなかったが時間が取れたんだと気持ちが切りかわり、帰路に着く。
長女は大阪の大学を卒業し静岡の家に戻ってきていた。
久方ぶりで家族らしい夕食に団欒の雰囲気を味わっていた。
娘は台所で夕食後の食器を洗ってくれていた。
わたしは静岡新聞を広げた。のんびりとページをめくると、
「常葉学園大学教育学部生涯学習学科新設、第1期生募集・社会人学生募集」の活字が目に飛び込んできた。
台所に居る娘に何気なしにいった。
「受けてみようかな」
「受けたら」
(一瞥されると思ったが、そうかそうきたか)
「そうね、受かるかわからないうちから悩んでもねえ」
「お金のことも頭脳のことも体力のことも受かったときに考えても遅くないよね」
つづく
2011年12月09日
ほだ火
「ほだ火」(山村留学 育てる村学園 同窓会報 第4号 2011年8月1日)
八坂学園10期修園生 6年生長女と4年生次女
保護者 池田庭子
あれは収穫祭の日だった。
眼下に稲を刈り取った田んぼが見えるなか、神主になりすました学園生が収穫の神事を見事にしている。昔ながらの脱穀を楽しむ人や、秋の日差しを浴びながら俄か床屋になったお父さんが娘の髪を切っている。私は膝の上に娘の頭を乗せさせて耳掃除をした。
ゆたかにゆったり流れる時間だった。
20年経った今も鮮明にあの光景を思い出す。
長女は新聞社に7年勤めた後看護師となり、「あの雲ななんという名だろう」と眺めながら八坂の学校にいっていたという次女は雪の研究でUSA大気研究所の研究員となった。
私は52歳で大学生になり生涯学習学科を専攻し、野外活動指導者資格・図書館司書・学芸員資格等6つも資格を取得し、美術の教員採用試験にも挑戦した。
在学中は中山間地に子どもの遊び場「たぬきむら」を創りNPO活動を学生たちとした。「たむきむら」の“た”は、たのしいなというように、ぬっくいな・きらきらと・むちゅうになって・らららららの願いを575に託した。
今は縁をいただいて、常葉学園大学内売店「Yショップ」の経営と子どもの居場所づくりで「駄菓子屋カフェ」を創っている。
これらすべて八坂が原点だと思っている。育てる会と娘たちがいた諏訪さん・仁科さんはじめ八坂の人々と自然に感謝し心よりお礼申し上げる。
八坂学園10期修園生 6年生長女と4年生次女
保護者 池田庭子
あれは収穫祭の日だった。
眼下に稲を刈り取った田んぼが見えるなか、神主になりすました学園生が収穫の神事を見事にしている。昔ながらの脱穀を楽しむ人や、秋の日差しを浴びながら俄か床屋になったお父さんが娘の髪を切っている。私は膝の上に娘の頭を乗せさせて耳掃除をした。
ゆたかにゆったり流れる時間だった。
20年経った今も鮮明にあの光景を思い出す。
長女は新聞社に7年勤めた後看護師となり、「あの雲ななんという名だろう」と眺めながら八坂の学校にいっていたという次女は雪の研究でUSA大気研究所の研究員となった。
私は52歳で大学生になり生涯学習学科を専攻し、野外活動指導者資格・図書館司書・学芸員資格等6つも資格を取得し、美術の教員採用試験にも挑戦した。
在学中は中山間地に子どもの遊び場「たぬきむら」を創りNPO活動を学生たちとした。「たむきむら」の“た”は、たのしいなというように、ぬっくいな・きらきらと・むちゅうになって・らららららの願いを575に託した。
今は縁をいただいて、常葉学園大学内売店「Yショップ」の経営と子どもの居場所づくりで「駄菓子屋カフェ」を創っている。
これらすべて八坂が原点だと思っている。育てる会と娘たちがいた諏訪さん・仁科さんはじめ八坂の人々と自然に感謝し心よりお礼申し上げる。
2011年12月04日
子どものころの遊び方
12月の第1日曜日いい天気です。クローゼットを整理していたら月刊誌「青少年」が出てきました。
月刊誌「青少年」は社団法人青少年育成国民会議(内閣府委嘱)の発行です。
下記は2007年2月発行のもので、声がかかり、寄稿したものです。
私は漁村で生まれました。
当時はまだ砂防用の松林が豊かで、松林の松の葉が風でかすかに揺れる音や、駿河湾の深海から打ち寄せる地から強い波の音に慣れ親しんで育ち、団塊世代の昭和20年初頭のにうまれた私は浜っこでした。
ある日、ちいちゃんとよっちゃんと海辺で遊びました。
スカートのすそをズロースのゴムに挟み込んで、浪打際で砂のお城を作っていました。
「おーい船があがるぞー」
シラス魚の漁師の声です。
私たちは砂の遊びを放り出して、伝馬船を浜に引き上げる作業に加わりました。
大の大人が幾人かいても波の力で足をずるずると波打ち際に持っていかれます。打ち寄せる波の乗せてひっぱり、引く波にずるずると波打ち際にひきよせられながら、力いっぱい足を踏ん張ります。
引っ張る太い綱から海の雫が落ちて、洋服はびしょびしょ、手は真っ赤。
漁師から作業歌が出ていたような遠い記憶があります。
「猫もまたいで通る」と言われるような雑魚は漁師の手で波打ち際に放り出されます。私たちは波打ち際でピチピチはねている雑魚を大急ぎで捕まえて、砂のお城に池を大急ぎで作り魚を入れます。もうひとつ池を作って魚を捕まえて遊びに大忙しです。
大漁のときは「ほれ、家に持ってけ」と手伝い賃代わりにバケツにいっぱい魚を入れてくれました。
フラフープが流行してやりすぎると腸捻転になると言われたころです。
浜で1本10円のアイスを売ったことも思い出します。小学5.6年生のころです。
今はもう、”浜行き”と言う行楽をする人もほとんど居なくなりましたが、当時は桜が咲く前の春の海に誘われて街の人たちが家族連れや町内会・隣組の宴会などで浜は大賑わいでした。
母の本家はタバコ屋で駄菓子・アイスも売っていました。わたしは浜でアイスを売れせてほしいと私から頼んだ気がしないまでもないのですが、アイス売りをしました。子どもだった私にはアイス売りも遊びだったのです。
お駄賃をもらうのも遊びの延長でした。
子どもの遊びの隣には大人の働く姿が身近にあり、子どもの遊びはいつの間にか大人の中に混じって、”仕事”になっていたのでした。
今思えば、自然との敬意に満ちたかかわりやコミュニケーションを含めて、遊びを通じて「生活とは」「生きるとは」にふれていたのではないかとおもうのです。
そして、私の子どものころのアソビはNPO活動につながりました。
子どもの成長にとってもっとも大切なことは、自然の中での遊びや、地域社会や、本物にふれる機会をと通じて、豊かな心を育む実践の場が必要と考えました。
里山の古民家を無償で借り受け子どもの遊び場〈たぬきむら〉を創って、「寒の味噌作り」、春浅い時期のヨモギを摘んで「団子三兄弟」など自然を生かした体験活動の場を提供しています。
〈たぬくむら〉を支えている常葉大学の学生は子どもたちとしっしょにカマドでご飯を炊きながら「こんな不便な時代に生まれなくてよかった」と声が漏れ聞こえてきたときには苦笑でした。
しかし、学生も子どもも里山の穏やかな空間に”はまって”いるようです。
子どもの健全育成をてーまにしている〈たぬきむら〉の名称には、「たのしいな、ぬっくいな、きらきらと、むちゅうになって、ららららら」と5.7.5にあわせて、5つの願いをこめました。
※学生たちとNPO法人とこは生涯学習支援センターを創って、理事長をさせていただいたときの寄稿です。

月刊誌「青少年」は社団法人青少年育成国民会議(内閣府委嘱)の発行です。
下記は2007年2月発行のもので、声がかかり、寄稿したものです。
私は漁村で生まれました。
当時はまだ砂防用の松林が豊かで、松林の松の葉が風でかすかに揺れる音や、駿河湾の深海から打ち寄せる地から強い波の音に慣れ親しんで育ち、団塊世代の昭和20年初頭のにうまれた私は浜っこでした。
ある日、ちいちゃんとよっちゃんと海辺で遊びました。
スカートのすそをズロースのゴムに挟み込んで、浪打際で砂のお城を作っていました。
「おーい船があがるぞー」
シラス魚の漁師の声です。
私たちは砂の遊びを放り出して、伝馬船を浜に引き上げる作業に加わりました。
大の大人が幾人かいても波の力で足をずるずると波打ち際に持っていかれます。打ち寄せる波の乗せてひっぱり、引く波にずるずると波打ち際にひきよせられながら、力いっぱい足を踏ん張ります。
引っ張る太い綱から海の雫が落ちて、洋服はびしょびしょ、手は真っ赤。
漁師から作業歌が出ていたような遠い記憶があります。
「猫もまたいで通る」と言われるような雑魚は漁師の手で波打ち際に放り出されます。私たちは波打ち際でピチピチはねている雑魚を大急ぎで捕まえて、砂のお城に池を大急ぎで作り魚を入れます。もうひとつ池を作って魚を捕まえて遊びに大忙しです。
大漁のときは「ほれ、家に持ってけ」と手伝い賃代わりにバケツにいっぱい魚を入れてくれました。
フラフープが流行してやりすぎると腸捻転になると言われたころです。
浜で1本10円のアイスを売ったことも思い出します。小学5.6年生のころです。
今はもう、”浜行き”と言う行楽をする人もほとんど居なくなりましたが、当時は桜が咲く前の春の海に誘われて街の人たちが家族連れや町内会・隣組の宴会などで浜は大賑わいでした。
母の本家はタバコ屋で駄菓子・アイスも売っていました。わたしは浜でアイスを売れせてほしいと私から頼んだ気がしないまでもないのですが、アイス売りをしました。子どもだった私にはアイス売りも遊びだったのです。
お駄賃をもらうのも遊びの延長でした。
子どもの遊びの隣には大人の働く姿が身近にあり、子どもの遊びはいつの間にか大人の中に混じって、”仕事”になっていたのでした。
今思えば、自然との敬意に満ちたかかわりやコミュニケーションを含めて、遊びを通じて「生活とは」「生きるとは」にふれていたのではないかとおもうのです。
そして、私の子どものころのアソビはNPO活動につながりました。
子どもの成長にとってもっとも大切なことは、自然の中での遊びや、地域社会や、本物にふれる機会をと通じて、豊かな心を育む実践の場が必要と考えました。
里山の古民家を無償で借り受け子どもの遊び場〈たぬきむら〉を創って、「寒の味噌作り」、春浅い時期のヨモギを摘んで「団子三兄弟」など自然を生かした体験活動の場を提供しています。
〈たぬくむら〉を支えている常葉大学の学生は子どもたちとしっしょにカマドでご飯を炊きながら「こんな不便な時代に生まれなくてよかった」と声が漏れ聞こえてきたときには苦笑でした。
しかし、学生も子どもも里山の穏やかな空間に”はまって”いるようです。
子どもの健全育成をてーまにしている〈たぬきむら〉の名称には、「たのしいな、ぬっくいな、きらきらと、むちゅうになって、ららららら」と5.7.5にあわせて、5つの願いをこめました。
※学生たちとNPO法人とこは生涯学習支援センターを創って、理事長をさせていただいたときの寄稿です。